2020年5月の事、当時の情勢でなかなか遠出が出来ない状況だった
ので関西圏内で日帰りで行ける廃線跡を探した結果、1994年まで
和歌山県に存在した野上電気鉄道(以下野上電鉄)を見つけたので、
和歌山県海南市までやって来ました。
 
…廃止時点で私は大学生だった事になりますから、乗ろうと思えば
乗れた物件なのですが、何故か放置したまま無くなってしまい、更に
25年以上が経過しております。果たしてどぅなりますやら?
そんな感じで今回はJR紀勢本線の海南駅からスタートしましょう。
野上電鉄の開通は大正時代の事。海南市から内陸部へ入った地域の
貨物輸送を主目的に、まずは軽便鉄道が敷かれました。

戦後も大手資本の傘下に入らず細々と営業
を続けてましたが、やはり自動車の台頭など
で赤字が続き、1994年に廃止されました。
海南駅近くの日方駅を起点に、ほぼ真東に
進んだ登山口駅まで11.4kmの路線です。
今回はWikipediaなどで駅のあった場所を
調べ、スマートフォンの地図アプリに落とし
込んできましたので、ソレを頼りに進んで
行けば迷う事はナイでしょう。
…我ながら少しハイテクになりましたね。
事前の調査で、日方側から手前の約半分は自転車OKの遊歩道として
整備され、残り半分はバイパス道路に転用されてる事が判明してます。
…まずは自転車で走って、残りは車にするのが良さそうですよ。
 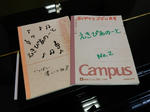
そして話はいきなり脱線するのですが、海南駅のコンコースにも最近
流行りの「駅ピアノ」があり、ソレに付属するノートがありました。
…コレに関しては従来の駅ノート設置駅以外にも確認されてる所が
何箇所があるのですが、駅ノートとして絵を描くか否かは人によって
判断が分かれる所です。
私もネタに詰まれば手を出すかも知れませんが、取り敢えず今日は
廃線跡を見に来たワケだし(絵の道具も持ってナイ)スルーしましょう。
 
海南駅に同居して市営の観光案内所があり、ココでレンタサイクルを
借りる事が出来ます。
…路線の中程に当たる沖野々駅跡付近まで遊歩道が整備されてる
らしいので、まずソコまで行って折り返しましょう。3時間(で往復可能
か?)で500円、全車が電動アシスト車のようです。コレは有り難い。
 
そんな感じで起点だった日方駅付近からスタートしますが、野上電鉄
の廃止後に海南駅も高架化され、当時とは全く雰囲気が変わってる
ものだと思われます。…左が日方駅があったと思われる地点ですが。
海南駅は西口の方に商店街やバスロータリーがあり、東口のこちらは
の方は住宅地なのかな?カナリの範囲が再開発されたようですが、
日方駅跡は更地のまま残ってる感じでした。
そして日方駅と海南駅は微妙に離れてるので、営業キロで0.2kmの
地点に連絡口駅なる駅が存在し、国鉄との乗り換えはココで出来た
ようです。…但し同駅は日方駅の構内扱い、いわゆる「隠れ駅」です。
ではココから約6km、まずは自転車での廃線跡巡りに出発ですよ。
起点の日方駅跡を出てJRの海南駅に近かった連絡口駅跡(何れも
再開発されて痕跡ナシ)を過ぎると、線路跡は東へ90度曲がります。
 
ココも再開発地域に含まれるようですが、線路跡に相当する部分は
何故か手付かずの状態で、小さ目の雑木が矢鱈と成長してますね。
線路のカーブに沿ってそのまま続いてますので、見れば分かる状況。
そんな環境だと猫の隠れ家に便利なのか、何匹かウロウロしてます。
…私は猫を発見するとまた脱線するワケですが、一番手前の子が
寄ってくるので人に慣れてるのかと思ったらいきなり殴られました。
別に君と喧嘩しようとか言うワケじゃないんだけど。
 
そして通りを隔てた所から、廃線跡が保存されてる区間になります。
…「健康ロード」と言う名前が付いており、海南市の市道のようですね。
全部で約6.1km。全区間の約半分に相当します。
道路標識によると「歩行者専用・軽車両可」と言う事なので、乗り物
は自転車まで。原付や自動二輪は不可です。
「健康ロード」だからサイクリング用と限定してるワケではなく、マラソン
やウォーキングもアリなのでしょう。途中にある「○○ひろば」と言うの
が元の途中駅跡で、恐らくは休憩場か何かになってると思われます。
 
途中に時々、地元の生徒さんが描いたと思われる壁画がありました。
海南市も海に面した町なので、コレは海や魚を題材にしてあります。
端っこに見えるキロポストもどきは、各区間の残距離を示す物。
線路跡だから当然、随所に踏切があった筈ですね。所々に右のような
車止め付きの交差点がありました。…廃線跡ではお馴染みの物です。
 
序盤の区間は、住宅地の隙間を縫うように線路が通ってた感じです。
…比較すると面白いのが上の2枚の画像です。
並立してるお家ですが、左のように玄関が反対側にある(と思われる)
のが廃止より前に建てられたお家、こちらに向いてるのが廃止後に
道路が整備されてから建ったお家と言う事になりますね。
…玄関から出たら直で線路とか、幾らローカル私鉄でも危険でしょ。
 
起点から1kmの地点にある「春日前広場」と言う地点に到着しました。
…先述の通り、この区間にある「○○広場」は全て元の駅跡です。
だからココはソノ名の通り「春日前」と言う駅だった事になりますね。
駅名票に似せた看板と地図があります。
近くに壁画がありますが、描かれている車両は1924年製のモハ20型
…24号車だと思われます。元は阪神の車両ですが、廃止時の1994年
まで使用されていました。
前面が丸くなった5枚窓の特異なデザインの車両で、この絵のように
クリーム色とオレンジ色のツートンカラーが同社の基本的な塗装です。
…しかし最末期には広告収入のためかチョコレート菓子の広告塗装
になっており、赤と白のド派手な色使いに商品のロゴがドーンと。
旧型の電車に似合わない事コノ上ありませんよね。当時から現在の
ようなラッピングの技術があったのか分からないのですが、どうも
コレが嫌で乗りに行かなかった記憶がありますよ。
 
花壇のように嵩上げした緑地帯や休憩用のベンチを備えた東屋が
ありました。緑地帯の段差はプラットホームのようにも見えますが、
コレは後から作られた物でしょう。
 
この付近を含めた同社の路線は、総じて「高野西街道」と呼ばれる
道路…国道370号線と平行しています。
左の画像で、手前の茶色い色が付けられてる部分が廃線跡。
ソノすぐ奥手が高野西街道で、ソノ名の通り延々と東へ走って行けば
高野山に至ります。
そして近くに学校がありました。和歌山県立海南高校です。
海南駅の東口から同校の校門まで1.2kmなので、高校生なら歩いて
通える距離でしょう。…しかし1駅だけ、旧型電車だらけのローカル
私鉄に乗れる環境だとすればどうでしょうね?
私がココの生徒なら、帰りに時間を合わせて乗って連絡口駅まで
乗ってみるとか、ヒマ潰しに終点の登山口駅まで行くとか、絶対に
やりそうな気がします。…てか現役当時なら現実に居たでしょ。
 
そんな事を考えつつ、次は元は幡川駅だった「幡川広場」です。
ココにある壁画の絵はデ10型…元は富山地鉄の車両だそうな。
鉄道線も充実してる筈の富山地鉄なのに、このデ10型は何と、元は
路面電車だそうで、ステップ部分を切り落として使ってたようですね。
…福井鉄道辺りへ行くと「その逆」も存在したりするワケですが、
鉄道車両の適材適所って意外と難しいのかも知れません。
まぁ廃車と中古車の需要と供給と言うのか、タイミングの問題かな。
 
ココは「駅の跡」と言う雰囲気はあまり無く、アスレチック運動も出来る
遊具などが備え付けられています。…そしてすぐ裏手は、先程と同じ
感じで高野西街道が並走しておりました。
…コレだけ道路が近いと、自動車が増えたらローカル私鉄は不利に
なって当たり前か。そして1993年に国の補助金が打ち切られたのが
廃止の決定打になってしまったようですね。
 
暫く行くと廃線跡は途切れてしまいました。…地図や航空写真で確認
すると、廃線跡を再利用した「健康ロード」も少し先から復活してるん
ですが、まずはコンビニの駐車場が出てきました。
…鉄道ってのは道路ほど急なカーブが造れませんから、線形からして
ココを突っ切ってた事になります。勿論、痕跡らしき物はありません。
その先は新しい住宅地になってます。10年ぐらい前に回った人の資料
を見ると、ココがまだ造成前の状態で、田んぼの畦道程度の道が確認
出来るんですが、以後に再開発されたようです。
 
…コンビニの駐車場は兎も角、住宅地で他所のお家の敷地を勝手に
通るワケにも行かず、ココは迂回して再確認出来る所から続けます。
道路が二股に分かれてる間に「健康ロード」の入口がありますね。
普通ならコノ地形で真ん中の道は必要ない筈であり、廃線跡ならでは
の状況になってます。
暫く行くと次の重根(しこね)駅跡…重根広場に到着しました。
 
基本的に単線だった野上電鉄線ですが、やはり幾つかの交換設備の
ある駅がありまして、最末期はココがそれの1つだった所です。
…航空写真で見ても明らかに交換設備の幅が見て取れました。
運転間隔は最末期で45分毎だったそうで、意外と多いイメージかな。
殆どの場合においてココで上下列車が交換していたようですが、全部
で11.4kmのうち起点から3.8kmの地点だから丁度1/3ですね。
…カナリ片寄ってる感じがしないでもありません。
更にこの先は勾配区間&駅間が短かくなるので日方ではカナリ間が
空く感じで、登山口はすぐに折り返すダイヤになる筈です。
 
駅の北側(右画像の上方)にある台形の土地が駅舎跡かと思ったん
ですが、古い動画(営業最終日の様子が幾つか上がってます)などを
見ると駅舎は反対側で、ココは倉庫(元は変電所)だったようです。
平行する道路をバスが走ってきました。…LED表示で行先が見にくい
ですが「登山口」となっており、コレが現在走ってる代替路線です。
地場資本の大十バス(愛称としてオレンジバスとも)による運行で、
本社と車庫は終点の登山口駅付近にありました(詳しくは後述)。
…些か雲行きが怪しくなってきましたので、先を急ぐ事にしましょう。
更に進むと廃線跡が切り通しになってる区間が出てきました。
 
…頭上に古めかしい感じの陸橋か掛かっていますが、明らかにコレは
線路を跨いでいた路地の跡でしょうね。
現在は「健康ロード」との間にもスロープが付いてましたので、登って
みましょう。電動アシスト車だから比較的ラクに行けます。
右の画像が海南方面を見た風景です。…電車だから架線が少し邪魔
かも知れませんが、なかなか良いアングルなので撮り鉄スポットにも
なってた事でしょう。
 
更に行くと、新しいバイパス道路との交差点に出ました。厳密には
まだ工事中のようですが、この付近の集落内を通る国道370号線を
迂回する「阪井バイパス」のようです。
…後で地図を見たら、ココは現地まで来る途中に通ってたわ。
広くなってしまった交差点の隙間に、気を付けて見ないと見落とす
サイズで廃線跡の「健康ロード」が通っています。
田舎の道路ってのは、実際の要不要はよく分からない場合も含めて
知らないうちに矢鱈と増えてる場合があって、つい3年ぐらい前の
カーナビには載ってナイ場合もありますよね。ココも然りでしたが。
後で詳しく述べますが、ココから先の廃線跡もカナリの区間が最近
になってバイパス道路に転用されたようです。
 
その先が紀伊阪井駅の跡地…現在は阪井広場になってる地点です。
左の画像で手前に写ってる建物は散髪屋さんなのですが、駅舎を
挟んですぐ向かいにお店がある情景が何となく想像出来ますね。
広場の真ん中に山本勝之助と言う人物の銅像がありました。…説明
を読むに、大正~昭和にかけてコノ付近で活躍した商人のようです。
近くに「山本勝之助商店」と言う会社が今でもあり、棕櫚(シュロ)を
材料としたホウキをなど生産してるとの事です。
元々野上電鉄の沿線は、タワシやロープ等の日用品の生産が盛んな
地域であり、同社も最初はソレらの製品を海南港まで運ぶのが主目的
だったそうな。…ローカル私鉄って起源は殆どソレですよね。
 
その山本勝之助商店がすぐ近所にあり、建物は文化財指定を受けた
貴重な物だと言うので見に行ってみました。…何となくNHHの旅番組
みたいなノリになってきましたが、なるほどレトロな雰囲気です。
古めかしい書体で書かれた板は看板ではなく、山本翁の座右の銘だ
そうで「手廻せねば雨が降る」と書かれています。
(※「が」は変体仮名…「可」を崩した所に「゛」)
…どんな意味なんでしょうね?ネットで「山本勝之助」と検索しても
「山本勝之助商店」としてホウキなどの通販広告が出て来るばかりで、
当人に関する情報が見つからないんですよ。
仕方がないから上の言葉をそのまま検索したら「猫が手で顔を洗うと
雨が降るってホント?」みたいなのが出ました。…似てるけど違うぞ。
察するに「備えあれば憂いなし」みたいなジャンルの言葉だと思うん
ですが、「備え無ければ憂いあり」風の逆説パターンなのかしらね?
また思わぬ所で思考的に脱線して時間を食った気がしますが、先を
続けます。間もなく全体の半分ぐらいに達する感じかな?
ココまで見てきた中には橋梁に関してはソレほど大きな物は無かった
ワケでして…
 
この程度の小さな橋梁が幾つか残っており、恐らく元はガーター鉄橋
だったと思われる物が、コンクリート製の橋桁に架け替えられてました。
その辺の事情は路線によって差がありますが、やはり鉄道用の橋桁
が残ってた方が面白い所です。しかし石積みの橋台は現役時代の
物がそのまま使われてる感じですね。
 
廃線跡脇の畑に、何やら果物が生ってる樹がありました。
…ビワのようですね。調べてみると海南市は全国有数のビワの産地
なのだそうです。ココは大規模な農場には見えないので家庭用かも
知れませんが、収穫期の少し前のようで袋を掛けてある物もあります。
 
更に進んだ所で国道へ出ました。先述の高野西街道…国道370号線
のようですが、ココからは完全に国道脇の歩道と化しており、駅跡を
休憩所にした施設は先程の「阪井広場」が最後のようです。
…現地にあるバス停に名前が残ってますが、この付近が沖野々駅跡
と思われる地点です。
周囲の環境がこんな感じなので、海南駅側は案内地図や壁画アート
があった「健康ロード」も、こちらの端には何の標識もなく些か寂しい
終わり方になってました。
 
交差点の名前にもなってるから、地名も同じ沖野々なんでしょう。
…野上電鉄が現在も残ってて、鉄道むすめの萌えキャラちゃんが
企画されていたら…名前は「日方のの」とかイイかも知れません。
暫く行くと、この地域では割と大きな貴志川に出ます。
右の画像の道路橋と平行して、野上電鉄の鉄橋も掛かっていた事に
なり、廃線後も暫くは橋脚などが残ってたらしいのですが、横断歩道
を渡って覗き込んでもソレらしい痕跡は発見出来ませんでした。
ココで全路線の約半分なのですが、この先は殆どがバイパス道路に
転用されてるらしので、レンタサイクルはココまでにして海南駅まで
折り返します。続きは車に乗って見て行く事にしましょう。
 
先程の沖野々駅跡で全路線の半分強の地点になるワケですが、ココ
から先は駅の数が矢鱈と多かったようですね。
当然の事に駅間は短かくなり、概ね800m程度の間隔が駅があった
事になります。町の中心部より遠い…市街地を離れた農村部の方に
駅が多いってのは珍しいかも知れません。
そして廃止後、段階的に国道のバイパスが延長されたり道路幅が
拡張されたりして、廃線跡の痕跡は殆ど無くなったようです。なので
全部の駅は紹介しきれませんが、取り敢えず続けましょう。
 
沖野々駅跡を過ぎて貴志川を渡った地点から暫くは、概ね左の画像
のような風景が続きます。元は田園風景の中を走る区間だっただろう
と想像されますが、道路にしてしまうとドコにでもある感じですね。
次の野上中駅は、消防団の倉庫に名前が残っており、Wikipediaの
位置情報から見るとこの敷地が駅舎跡だと推測されます。
…ちなみに駅で言うと次の北山駅までが海南市、以降は紀美野町
(旧野上町)になります。廃線跡の再利用の方法は自治体によって
変わる事も多いので、こちらはバイパス道路になったのかも。
 
そして紀伊野上駅跡。ココは大正5年の開業時は終点だった駅で、
後の昭和3年に登山口駅まで延長されて途中駅になりました。
交換設備もあったようですが、末期は本数が減って朝夕のラッシュ
(ソレなりの)時間帯のみ上下交換が行われてたようです。
…線路跡がバイパス道路になったと言う事は、集落内を通ってる
こちら側の旧道に面して駅舎があった事になりますが、平行して
流れる貴志川による浸食で土地に高低差があります。
だから駅跡付近にも微妙な段差があるんですよ。資料写真で見ると
一般的な平地の駅なのですが、現在では詳しい事は分かりません。
 
続く動木(とどろき)駅の跡も、現在は道路標識に地名が残るだけに
なってました。
バイパス道路は右のような感じです。…10年ほど前に廃線跡を探索
した人のサイトを見ると、この付近はバイパスがまだ開通しておらず、
草に埋もれた鉄橋の跡などが残ってたようですが、面影はありません。
現役当時の線路も、貴志川に沿って走る景色のいい区間だったそうな。
…こんな感じで終点まで行ってしまうのは面白くないので、ココで付近
に残る保存車両を見に行く事にします。私にとっては比較的近い地域
の筈が、今まで知らなかったんですよ。ちょっと楽しみですね。
 
終点の1つ手前だった下佐々駅跡の近くに「くすのき公園」と言う公園
があります。公園そのものは廃止前からあったらしいですが、廃止時
ままで走ってた車両がココに保存されいるとき聞いてきました。
 
同社ではモハ31号と呼ばれていた車両ですが、元は阪神の1130号
として昭和9年に製造された車両だそうな。…更に古い大正時代の
車両を鋼体化したグループです。昭和38年に野上電鉄へ譲渡され、
廃止時まで走ってました。
クリーム色とオレンジ色のツートンカラーは末期の野上電鉄の一般的
な塗装でしたが、本家の阪神電車では昭和33年頃からコレに近い
いわゆる「赤胴車」が登場しており、移籍前からこの色だった可能性
もあります(調べたけど分からんかった)。
 
戦前の阪神電車は、他の会社より車両のデザインが洗練されており
「阪神モダニズム」なんて言う言葉もあったそうですが、この車両も
側面の窓上に明かり取りの小窓が付く洒落たデザインになっます。
阪神在籍時の末期には、後に「ジェットカー」として登場する高性能
車両(カルダン駆動)の試験車にもなったようですが、野上電鉄は
軌間が1067mmなので南海の派生品の台車に取り換えられています。
説明書きに寸法も書いてありますが、14m弱ってのはカナリ小型です。
…しかし幅が2470mmって、昭和中期の近鉄大阪線などの車両と同じ
なのですが、正面からみると明らかに狭い。横に張り出したステップ
込みのサイズかも知れませんな。
社紋はコレが野上電鉄の物なのか?苦しいけど「野上」と読めない
事はありません。
 
そして今のモハ31号を「保存車①」として、ココから100mほど離れた
地点に「保存車②」が存在するとも聞いております。10年ほど前の資料
から「今でもあるのか?」を確認して、アタリを付けています。
近いので車はココに置いて、歩いて探しに行きましょう。
…ストリートビューで見たのと同じように、屋根付き駐車場の建物の
隙間からモハ31号と同じ色の車体が見えてますね。続いてはコレです。
 …先程の「くすのき公園」から100m …先程の「くすのき公園」から100m
ほど離れた地点に、もぅ1両の保存車
があると聞いて歩いてきました。
道路から見るとガレージの隙間から
僅かに車体が見える程度でしたが、
反対側は田んぼなので全体がよく
見えます。
コレは野上電鉄ではモハ20型の27号
だった車両だそうな。
元は阪神電鉄の701型として、やはり戦前に木造車両を鋼体化して誕生
した形式です。小型で使いやすかったようで、廃止時まで走ってました。

資料によると「個人所有」になっており、
付近で開業してるお医者さんの持ち物
なんだそうです。…しかし現場にあった
建物は、資料と同じなのにエステサロン
の看板が出ていました。
…病院は無くなって別の人が入居した
のか、商売替えしたのかは不明ですが、
車両はそのまま残ったようですね。
 
…テレビの旅番組だと、偶然に持ち主が通りかかって「良かったら
近くで見ますか?」と鍵を開けてくれたりするもんですが、そんな都合
のいい展開にはならず、金網の隙間から勝手に見学しております。
やはり屋根付きなので保存状態はイイですね。コレまた先に見てきた
資料によると車両本体はタダだったようですが、輸送費に(20年ほど
前の話で)200万円程度掛かったそうな。
線路と屋根の建設費も、一般人の感覚からすると高価でしょうな。
内部が見学出来るように階段も取り付けてあります。
…しかし一緒にあるキロポストが謎ですね。一般的には500m単位の
筈であり、11.4とか0.03とか細かすぎない?
小数点第2位まで数てたとしたら、10m置きに建ってた事になるぞ。
 
そんな感じで2両の保存車があった下佐々駅跡から1km足らずの所
が終点の登山口駅跡になります。
野上電鉄も廃止後にバス転換され、現在は概ね元の鉄道と平行する
ルートで大十バスと言う地場資本のバス会社が路線バスを走らせて
います。駅跡は同バス会社の車庫などになったようですね。
 
元は野上電鉄にもバス部門がありましたが、鉄道の廃止後に分社化
して、現在は野鉄観光と言う観光バス会社として存続しています。
…大十バスは地場の運送会社が親会社になるそうで、専門分野か
地域密着かで後者が選ばれたような感じなのかも知れません。
車庫前の商店が、いかにも田舎の終着駅の駅前な雰囲気ですね。
と言う事で、海南駅前から辿って来た野上電鉄の廃線跡を探る旅は
ココまでとなります。
 
…ついでの事に子供の頃からの疑問を1つ解決しておきましょう。
「登山口駅」とは言うものの、どこ山の登山口なのか?
付近に昔からありそうな看板がありました。駅から6.5kmの所に生石
(おいし)高原と言う所があるようです。
隣県と言う比較的近くに住んでる筈なのですが、初めて聞いたかな。
例えば学校の休み時間の雑談とかで「今度、生石高原へハイキング
に行こうぜ。」ってな話は、少なくとも 私は聞いた事がありません。
…野上電鉄も、その生石高原への観光用に特化した路線ではナイし。
そして更に「おまけネタ」なのですが、野上電鉄の廃止後に上記の
2両の保存車とは別に、阪神電鉄へ里帰りした車両があると言う話を
聞きました。
別に日に少し探りに兵庫県尼崎市へ行ってきましたので、その報告
へと続きます。
 
阪神本線の尼崎センタープール前と言う駅で降ります。…同駅は確か
「長い名前の駅」として、一時期は日本一だったような気がします。
…ちなみにプールとは言っても水泳用のソレではなく競艇場の事です。
レース開催日には混雑するのかも知れませんが、ソレ以外では閑散と
した駅ですな。
この付近の阪神線は高架になっており、その高架下に保存車があると
聞いております。改札を出て三宮方向へ歩いてみましょう。
 
暫く行くと左のような看板が出てきました。
「運輸部教習所(動力車操縦者指定養成所)」と書いてありますな。
…平たく言えば電車の運転士さんになる人が訓練を行う所でしょう。
大手の鉄道会社ならコノ手の施設を自前で持ってる所は多い筈です。
勿論、一般人が勝手に敷地内に入れる所ではありませんので、柵の
外から見てみますと、コレも訓練施設の一部なのか架線や信号機
などの設備を集めた一角があります。
 
そして同じ効施設の敷地内に、探していた車両がありました。
いかにも古めかしい、茶色い塗装の小型電車が2両並んでますな。
尼崎センタープール前駅は2面4線の駅であり、航空写真で測ったら
駅の幅は30mありました。…14m前後の車両を横向きに収めるには
充分なサイズなのでしょう。
…当然の事にフェンス越しにしか見れないのですが、機会は少ない
ものの一般に公開される事があるらしく、説明用のプレートらしき物
があるのも確認出来ます。
調べてみた所、やはり同社が行なう親子連れ(子供は小学生)を対象
とした体験スクールみたいな企画で公開された事があるようです。
…小学生の子供が必要な時点で、かなりハードルは高いですね。
 仕方がナイので公道から見える状態だけ 仕方がナイので公道から見える状態だけ
写真に撮って、後は説明文で埋めてしまう
事にしますが、まずは向かって左の「1150」
と書かれた車両からです。
…コレは元阪神の1100型のうちの1両で、
野上電鉄ではモハ32号となった車両です。
現地の「くすのき公園」で見たモハ31号
と同型の車両だと思われますが、塗装を
変えるとイメージも変わりますね。
分かりにくいですが側面の明かり取りの窓
が確認出来ると思います。
 続いてが向かって右の「604」と書かれた 続いてが向かって右の「604」と書かれた
車両です。コレまたフェンス越しなんですが
車端部を丸くした形状で、正面から見て
5枚の窓があるデザインになってますね。
このスタイルは当時の流行だったようです。
こちらもは阪神では601型、野上電鉄では
モハ24号と呼ばれていた車両で、大正末期
に古い半鋼製の電車を鋼体化した物です。
こちらは野上電鉄では1点物だったので
同僚の保存車はありませんが、廃線跡
(健康ロード)の春日前広場付近にあった
壁画に同車両の絵が描かれていました。
…両者ともドノ程度まで復元されてるのか分かりませんが、本家の
大手私鉄の仕事ですから、カナリ原型に近い物だと思われます。
当日はお天気が良すぎて陽射しが強く、写真の明暗がキツく出て
しまいました。…撮りに行くなら曇りの日がオススメかも知れません。
てか子供連れ以外で公開されるイベントがあれば好都合なのですが。
|
|