2020”N3Œژ‚جƒ_ƒCƒ„‰üگ³‚©‚ç“Œ“ْ–{‘هگkچذ‚ة‚و‚éڈي”ضگü‚ج‹xژ~‹وٹش
‚ئ‚µ‚ؤژc‚ء‚ؤ‚¢‚½•x‰ھپ`کQچ]‚ھ‚و‚¤‚â‚ٹJ’ت‚µپA“Œ‹پ`گه‘ن‚ج‘Sگü‚ھ
Œq‚ھ‚è‚ـ‚µ‚½پB
‚»‚µ‚ؤ“¯”N4Œژ‚جژ–پA‚»‚ج“Œ“ْ–{‘هگkچذ‚ة‘j‚ـ‚ê‚ؤڈو‚è’ׂµ‚ھڈo—ˆ‚ؤ
‚ب‚©‚ء‚½‹وٹش‚ةڈو‚é‚ׂپA‚¢‚ي‚«پ`–¼ژو‚ض‚ئ—·‚µ‚ـ‚µ‚½پB
‚»‚ج‚¤‚؟’أ”g‚ج”يٹQ‚ًژَ‚¯‚ؤ“à—¤•”‚ضگüکH‚ًˆعگف‚µ‚½گV’nپ`•l‹g“c
‚ج‹وٹش‚ًگV‹Œ‚ئ‚à‚ة’T‚ء‚ؤ‚«‚½•”•ھ‚ج•ٌچگ‚إ‚·پB
‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إگو‚¸‚حڈو‚è“S•”•ھ‚ج‘ٹ”n‰w‚©‚çƒXƒ^پ[ƒg‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
‚؟‚ب‚ف‚ةƒRƒR‚حگV’n‰w‚ـ‚إ‚ھ•ں“‡Œ§پAچ⌳‰w‚©‚ç‚ح‹{ڈ錧‚إ‚·پB
 
‘ٹ”n‚ـ‚إ‚ح”نٹr“I‘پ‚‚ة•œ‹Œ‚µ‚½‹وٹش‚إپA‘O‰ٌ‚ة—ˆ‚½ژ‚àڈو‚è‚ـ‚µ‚½پB
…“–ژ‚ح”ٍ‚ر’n“I‚ة•œ‹Œ‚µ‚ؤ‚éڈَ‹µ‚¾‚ء‚½‚ج‚إپAٹm‚©ژش—¼‚ح—¤‘—‚إ
‰^‚ٌ‚¾”¤‚إ‚·‚و‚ثپB
ƒ\ƒŒ‚ظ‚ا‚جژù—v‚ھƒiƒC‚ج‚¾‚©‚çپAŒ´ƒm’¬‚ة•ْ’u‚³‚ê‚ؤ‚é651Œn‚àژg‚ء‚ؤ
‚â‚ê‚خ—ا‚©‚ء‚½‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·‚ھپAگ®”ُڈo—ˆ‚ب‚¢‚ئ–³—‚إ‚·‚©پH
 
‚»‚µ‚ؤƒRƒmگو‚ھپA•œ‹ŒŒم‚ةƒ‹پ[ƒg‚ً‘ه•‚ة•دچX‚µ‚ؤگV‚µ‚Œڑگف‚³‚ꂽ
‹وٹش‚ة“ü‚è‚ـ‚·پB…‹îƒ–—ن‚ً‰ك‚¬‚ؤژں‚جگV’n‚ة“’…‚·‚éژè‘O‚ةپAگüکH
‚ھ‘ه‚«‚چ¶پiگ¼پj‚ةƒJپ[ƒu‚µ‚ؤ‚é’n“_‚ھ‚ ‚ٌ‚إ‚·‚ھپAƒRƒR‚©‚ç‚إ‚·‚و‚ثپB
Œ³‚جگüکH‚ح‹ب‚ھ‚炸‚ة’¼گi‚µ‚ؤ‚½ژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ھپAƒ\ƒmگو‚ة‚ ‚ء‚½
‹Œ—ˆ‚جگV’n‰w‚حپAگkچذ”گ¶ژ‚ج’أ”g‚إŒ×گü‹´ˆبٹO‚جژ{گف‚ھ‘S‚ؤ
‰ں‚µ—¬‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
‚ب‚ج‚إŒ»چف‚جگV’n‰w‚ح300‚چ‚ظ‚ا—£‚ꂽڈٹ‚ةگV‚µ‚‘¢‚ç‚ꂽ•¨‚إ‚·پB
 
گkچذ”گ¶‚ج’¼‘O‚ة“¯‰w‚ة’âژش‚µ‚ؤ‚¢‚½“dژشپiE721Œn‚ج4—¼•زگ¬پj‚àپA
’أ”g‚ة‚و‚ء‚ؤگ”ڈ\ƒپپ[ƒgƒ‹—¬‚³‚êپA‘ه”j‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚·پB
’¼Œم‚ة•ٌ“¹‚³‚ꂽƒjƒ…پ[ƒX‰f‘œ‚إپA–³ژc‚ة“]‚ھ‚ء‚ؤ‚éژش—¼‚ًŒ©‚ؤ
ƒVƒ‡ƒbƒN‚ًژَ‚¯‚½گl‚à‘½‚©‚ء‚½‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپAڈو‹q‚ئڈو–±ˆُ‚حٹù‚ة
”ً“‚ؤ–³ژ–‚¾‚ء‚½‚ج‚ھ•sچK’†‚جچK‚¢‚إ‚µ‚ه‚¤‚ثپB
‚»‚µ‚ؤگkچذŒم‚ج•œ‹Œ‚ة”؛‚¢گüکH‚ھ“à—¤‘¤‚ة•t‚¯‘ض‚¦‚ç‚ê‚éژ–‚ة‚ب‚èپA
گV’nپEچ⌳پEژR‰؛‚ج‚R‰w‚ئ‘±‚•l‹g“c‚جژè‘O‚ـ‚إ‚ھگVگü‚ئ‚µ‚ؤٹJ‹ئ
‚·‚éژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
 
–w‚ا‚ج‹وٹش‚ھچ‚‰ثگü‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¨‚èپA“r’†‚ج‚Q‰w‚àچ‚‰ث‰w‚إ‚·پB‰E‚ھ
چ⌳‰w‚إ‚·‚ھپAژش‘‹‚ج‰Eژè‚ة‚حٹC‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‹——£‚ح–ٌ1.7kmپB
‹Œ—ˆ‚جچ⌳‰w‚حƒRƒR‚©‚ç1km’ِ“x—£‚ꂽٹC‘¤‚ة‚ ‚ء‚½‚ج‚إپAٹm”F‚ح
ڈo—ˆ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھ‰E‚ج•—Œi‚ج’†‚ة‚ ‚ء‚½ژ–‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚ثپB
‘O‰ٌ‚ج–K–âژ‚ح‘ٹ”nپ`•l‹g“c‚ج‘مچsƒoƒX‚إƒRƒR‚ً’ت‚ء‚½ƒڈƒP‚إ‚·‚ھپA
ژش‘‹‚©‚çŒڑگف’†‚جچ‚‰ثگü‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پB
…ژہچغ‚ةٹJ’ت‚µ‚ؤ—ٌژش‚إ—ˆ‚ê‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½پB‚ئŒ¾‚¤‚ج‚ح‘¼ڈٹژز‚ج
ژ„‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚àٹ´“®“I‚بژ–‚إ‚·‚©‚çپA’nŒ³‚ج•û‚جٹى‚ر‚ح‘ه•د‚ب•¨‚¾‚ئ
ژv‚¢‚ـ‚·‚وپB
 
گüکH‚ھ“à—¤•”‚ةˆعگف‚³‚ꂽژ–‚إپAڈ¬چ‚‚¢‹u‚ب‚ا‚حƒgƒ“ƒlƒ‹‚إ”²‚¯‚é
‹وٹش‚à‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAٹT‚ثچ‚‰ثگü‚ج‰سڈٹ‚ھ‘½‚¢‚إ‚·‚ثپB
‘±‚ژR‰؛‰w‚حŒًٹ·گف”ُ‚ج‚ ‚铇ژ®ƒzپ[ƒ€‚ج‰w‚إ‚µ‚½پB
…–]‰“‚إژB‚ء‚ؤ‚é‚©‚ç’Z‚©‚Œ©‚¦‚ـ‚·‚ھƒzپ[ƒ€’·‚ح‚U—¼•ھپA‚»‚µ‚ؤ
“ء‹}پu‚ذ‚½‚؟پv‚ھ10—¼•زگ¬‚ب‚ج‚إ—LŒّ’·‚ح200‚چˆبڈم‚ ‚è‚ـ‚·پB
ƒRƒR‚ـ‚إ‚ج‚R‰w‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حŒم‚©‚ç–ك‚ء‚ؤ‚«‚ؤپAگV‹Œ—¼•û‚ج’n“_‚جŒ»ڈَ
‚ًٹm”F‚·‚é—\’è‚ة‚µ‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·‚ج‚إپAچ،‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـڈو‚è’ت‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
 
گVگü‚جچ‚‰ث‚©‚ç’nڈم‚ةچ~‚èپA‰Eپi“Œپj‚ضڈ‚µگU‚é‚ئ‹Œگü‚ة–ك‚è‚ـ‚·پB
…چ¶‚ج‰و‘œ‚ھچ‡—¬’n“_‚ئŒ¾‚¤‚©پAƒRƒR‚©‚çگو‚ھڈ]—ˆ‚جگüکH‚¾‚ئ
ژv‚ي‚ê‚é’n“_‚إ‚·پB’nگ}‚إŒ©‚é‚ئŒ³‚جگüکH‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ‘–‚ء‚ؤ‚½“¹کH
‚ھ‚ ‚é‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB•—Œi‚ًٹo‚¦‚ؤ‚¨‚¢‚ؤپAŒم‚إŒںڈط‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
ڈ‚µ‘–‚é‚ئ•l‹g“c‚ة“’…پBƒRƒR‚ح’أ”g‚ج”يٹQ‚ًژَ‚¯‚ب‚©‚ء‚½‚و‚¤‚إپA
گج‚ب‚ھ‚ç‚ج’nڈم‰w‚ھژc‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB
 
‘O‰ٌ‚ة—ˆ‚½ژ‚àپAگه‘ن‘¤‚حƒRƒR‚©‚ç•œ‹Œ‚µ‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ھ‘مچsƒoƒX‚ح
گو‚جکj—‚ـ‚إ‘–‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚ؤپA•l‹g“cپ`کj—‚حڈd•،‚µ‚ؤ‚ـ‚µ‚½‚ثپB
کj—‚ب‚ç‰w‘O‚ةƒoƒX‚ھ’…‚¢‚½‚炵‚¢‚ج‚إ‚·‚ھپAڈ‚µ‚إ‚à“S“¹‚إ
چs‚«‚½‚¢ژ„‚حپu‘مچsƒoƒX‚ج•l‹g“cƒoƒX’âپv‚إچ~‚肽‚ٌ‚إ‚·‚وپB
…ƒoƒX‚ح‚Qkm‚ظ‚ا“à—¤‚جچ‘“¹‚Uچ†گü‚ً‘–‚é‚ج‚إپAچإ’Z‹——£‚ج’n“_
‚إ‚àƒJƒiƒٹ—£‚ê‚ؤ‚ـ‚µ‚ؤپA“c‚ٌ‚ع“¹‚ً‰„پX‚ئ•à‚«‚ـ‚µ‚½‚يپB
 
‚±‚±‚ـ‚إ—ˆ‚ê‚خڈي”ضگü‚ئ‚µ‚ؤ‚جڈI“_‚إ‚ ‚éٹâڈہ‚ـ‚إ‚·‚®‚¾‚µپAڈو‚èٹ·‚¦
—\’è‚ج–¼ژو‚إ‚àژc‚è30•ھ‚ًگط‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB‰w–¼•[‚ةŒ»‚ꂽگه‘ن‚ج
‚ن‚éƒLƒƒƒ‰پu‚ق‚·‚رٹغپv‚ھپA‹كچx‹وٹش‚ة“ü‚ء‚½ژ–‚ً‹³‚¦‚ؤ‚‚ê‚ؤ‚ـ‚·پB
…‚؟‚ه‚ء‚ئ‘پ‚¢‚¯‚اچ،‚ج‚¤‚؟‚ة’‹گH‚ة‚µ‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚ه‚¤پB’©‚ة‚¢‚ي‚«‚إ
”ƒ‚ء‚ؤ‚«‚½‰w•ظ‚جپuٹڈ‚أ‚‚µپv‚إ‚·پBگط‚èگg‚ج“‚—g‚°‚ھ”ü–،‚©‚ء‚½‚بپB
‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إٹâڈہ‚ً‰ك‚¬‚ؤ–¼ژو‚إ‰؛ژشپBƒRƒŒ‚إ”Oٹè‚جڈي”ضگüٹ®ڈو‚à
’Bگ¬‚ئ‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB
…ژv‚¦‚خƒRƒm‹وٹش‚حپAچ‚چZ‚P”Nگ¶‚ج‰ؤ‹x‚ف‚ةڈو‚è“S—·چs‚ً‚â‚ء‚½چغپA
ŒSژRپ`‚¢‚ي‚«پ`گه‘ن‚ئ”ض‰z“ŒگüŒo—R‚إچsکH‚ً‘g‚ٌ‚إ‚½‚ج‚ًپA”و‚ê‚ؤ
گVٹ²گüƒڈپ[ƒv‚µ‚½ژ–‚©‚çگ”‚¦‚ê‚خ30”N‰z‚µ‚ج–ع•W‚¾‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚وپB
“Œ“ْ–{‘هگkچذ‚ً‹²‚ٌ‚إ‚µ‚ـ‚ء‚½‚ھŒج‚ةƒJƒiƒٹژٹش‚ھٹ|‚©‚è‚ـ‚µ‚½پB
 
–¼ژو‚©‚çگه‘ن‹َچ`ƒAƒNƒZƒXگü‚إگه‘ن‹َچ`‚ضڈo‚ؤپAƒRƒR‚إƒŒƒ“ƒ^ƒJپ[‚ً
ژط‚è‚ـ‚·پB…ƒRƒR‚©‚ç‚حپA‰w‚إŒ¾‚¤‚ئگV’nپ`•l‹g“c‚ـ‚إ‚جˆعگف‹وٹش‚ً
ژہچغ‚ةژش‚إ‘–‚ء‚ؤٹm”F‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤
گkچذŒم‚ةگüکH‚ً•œ‹Œ‚³‚¹‚éچغپA’nŒ³‚ج—v–]‚إ“à—¤•”‚ً’ت‚郋پ[ƒg‚ة
•د‚ي‚èپAچ⌳پEژR‰؛‚ج‚Q‰w‚ح‚Pkm‚ظ‚ا—£‚ꂽ’n“_‚ةچؤŒڑ‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
…‘O‰ٌ‚ة—ˆ‚½ژ‚ةپA‘مچsƒoƒX‚جژش‘‹‚©‚çŒڑگف’†‚جچ‚‰ثگü‚ًŒ©‚½ژ
‚©‚çپuٹJ’ت‚µ‚½‚çٹO‚©‚ç‚àŒںڈط‚µ‚ؤ‚ف‚و‚¤پv‚ئژv‚ء‚ؤ‚½‚ٌ‚إ‚·‚وپB
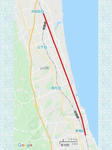 
Google‚ج’nگ}‚إŒ©‚ؤ‚ف‚é‚ئپAŒ³‚جگüکH‚حٹCٹف‚ة‹ك‚¢ڈٹ‚ً‚ظ‚عˆê’¼گü
‚ة’ت‚ء‚ؤ‚½ژ–‚ھ•ھ‚©‚è‚ـ‚·پB
…‚T”N‘O‚ج“¯‚¶‹وٹش‚ج•¨‚ئ”ن‚ׂé‚ئپA‚â‚ح‚èگ³ژ®‚ةŒˆ‚ـ‚ء‚½کHگü‚ة
ڈ‘‚«ٹ·‚¦‚ç‚ê‚ؤ‚éƒڈƒP‚إ‚·‚ھپA“–ژ‚ةچq‹َژتگ^‚ًŒ©‚ؤژ„‚ھگ„’肵‚½
ƒ‹پ[ƒg‚ة‹ك‚¢‚إ‚µ‚هپB
 
ژو‚èٹ¸‚¦‚¸‹َچ`‚©‚ç‹ك‚¢•û‚©‚çژn‚ك‚ؤپAڈ‡‚ة“ى‰؛‚µ‚ؤچs‚±‚¤‚ئپA
‚ـ‚¸‚ح•l‹g“c‰w‚ةŒü‚©‚¢‚ـ‚µ‚½پB…30•ھ‚ظ‚ا‚إ’…‚«‚ـ‚µ‚½‚©‚بپB
ƒRƒR‚ًŒںڈط‚جƒXƒ^پ[ƒg’n“_‚ة‚µ‚ـ‚·پB
ƒJپ[ƒiƒr‚إپA‚ـ‚¸‚حژں‚جژR‰؛‰w‚ًŒںچُ‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB
“¯‰w‚ھگV‹KٹJ‹ئ‚µ‚½‚ج‚ح2016”N‚جژ–‚¾‚©‚çپAƒ\ƒŒˆبچ~‚ةگ»‘¢‚³‚ꂽ
‹@ژي‚ب‚çپAƒfپ[ƒ^‚àگV‚µ‚¢•¨‚ھڈo‚锤‚إ‚·‚ثپB
ƒŒƒ“ƒ^ƒJپ[‚جژشŒںڈط‚ًŒ©‚é‚ةپAڈ‰“x“oک^‚ح•½گ¬30”N‚¾‚©‚ç‚Q”N‘O‚©پB
ڈيژ¯“I‚ةچl‚¦‚ê‚خƒJپ[ƒiƒr‚à“¯ژٹْ‚ةگ»‘¢‚³‚ꂽ•¨‚إ‚µ‚ه‚¤پB
ƒ‹پ[ƒg‚ئ‚µ‚ؤ‚ح“¹•‚ھچL‚¢ٹ²گü“¹کH‚ًژwژ¦‚³‚ê‚ؤ‚ـ‚·‚ھپAڈo—ˆ‚éŒہ‚è
گج‚جگüکH‚ة‹ك‚¢پi‚ئژv‚ي‚ê‚éپj“¹‚ً‘–‚ء‚ؤ‚¢‚ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
…ƒRƒR‚©‚ç‚حگkچذŒم‚ةگVگü‚ةˆعگف‚³‚ꂽ‹وٹش‚ج’²چ¸‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپA
‹Œگü‚ج”pگüگص‚âگV‚µ‚¢‰w‚ب‚ا‚ًŒ©‚ؤچs‚«‚ـ‚·پB
 
•l‹g“c‰w‚©‚çڈي”ضگü‚جگüکH‚ة‰ˆ‚ء‚ؤ“ى‚ض900‚چ‚ظ‚اچs‚‚ئپA“à—¤‘¤‚ض
‘ه‚«‚ƒJپ[ƒu‚µ‚ؤ‚¢‚éڈٹ‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
گو’ِژہچغ‚ةڈو‚ء‚ؤ—ˆ‚½“dژش‚جژش“à‚©‚猩‚¦‚½‚±‚ج’n“_‚إٹشˆل‚¢ƒiƒC
‚ئژv‚¤‚ٌ‚إ‚·‚ھپA‹Œگü‚جگüکH‚ح‹ب‚ھ‚炸‚ةگ^‚ء’¼‚®“ى‰؛‚µ‚ؤ‚¢‚½‚ئ
ژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
…ژ„‚àگFپX‚ئ”pگüگص‚ً–K‚ث‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ج‚إپAƒ\ƒm–ع—ک‚«‚حڈo—ˆ‚é
‚و‚¤‚ة‚ب‚è‚ـ‚µ‚½پB‰E‚ج‰و‘œ‚جپA“c‚ٌ‚ع‚إ‚àڈZ‘î’n‚إ‚àƒiƒC•sژ©‘R‚ة
چ×’·‚¢“y’n‚ھƒ\ƒŒ‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
•t‹ك‚ً’T‚µ‚ؤ‚ف‚é‚ئپAچ‘“S‚ج“y’n‚ئ‚ج‹«ٹE‚ً‹L‚·پuچHپvƒ}پ[ƒN‚جچY‚ھ
Œڑ‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پBٹشˆل‚¢ƒiƒC‚و‚¤‚إ‚·‚وپB
 
‚ب‚é‚ׂ‹Œگü‚ة‰ˆ‚ء‚½“¹‚ً‘–‚肽‚©‚ء‚½‚ج‚إ‚·‚ھپA“r’†‚إ‹ب‚ھ‚ء‚½‚è
ڈW—ژ‚ة“–‚½‚ء‚½‚è‚·‚é‚ج‚إپAژو‚èٹ¸‚¦‚¸‚حƒJپ[ƒiƒr‚إگف’肵‚½ژں‚ج‰w
…Œ»چف‚جژR‰؛‰w‚ضŒü‚©‚ء‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
2016”N‚ةٹJ’ت‚µ‚½گV‚µ‚¢چ‚‰ثگü‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBژR‰؛‰w‚ح‚»‚ج‚ـ‚ـ
چ‚‰ث‰w‚ئ‚µ‚ؤگV‚µ‚‘¢‚ç‚ꂽ‚و‚¤‚إ‚·پB
•t‹ك‚ة‚حŒِ–¯ٹظ‚âƒhƒ‰ƒbƒOƒXƒgƒA‚ب‚ا‚à‘¢‚ç‚êپAگV‚½‚ب‰w‘O‚ئ‚µ‚ؤ‚ج
چؤٹJ”‚ھگi‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚µ‚½پB
 
‰w‚جچ\‘¢‚ئ‚µ‚ؤ‚حپAƒRƒŒ‚àگو’ِ‚ج“dژش“à‚©‚猩‚½’ت‚èپAŒًٹ·گف”ُ‚ج‚ ‚é
“‡ژ®ƒzپ[ƒ€‚ج‰w‚إ‚·پB
‰E‚ح‰üژD•t‹ك‚إ‚·‚ھپA“–‘R‚جژ–‚ة‚ـ‚¾گV‚µ‚¢•µˆح‹C‚إ‚·پB
ٹبˆصˆد‘ُ‰w‚ب‚ھ‚ç‚ف‚ا‚è‚ج‘‹Œû‚ھ‚ ‚ء‚ؤپA‰üژDƒ‰ƒbƒ`‚ج‘م‚ي‚è‚ةSuica
‚جƒJپ[ƒhƒٹپ[ƒ_پ[‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
…‚±‚ê‚©‚ç‘¢‚ç‚ê‚é‰w‚ء‚ؤ‚ج‚حپAچإڈ‰‚©‚çƒXƒچپ[ƒv‚âƒGƒŒƒxپ[ƒ^پ[‚ً
‘•”ُ‚µ‚ؤ‚é‚إ‚µ‚ه‚¤‚©‚çپA–³‘ت‚ج‚ب‚¢ƒXƒ}پ[ƒg‚ب‘¢‚è‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ثپB
 
‚»‚µ‚ؤŒ»چف‚جژR‰؛‰w‚©‚ç“Œ…ٹCٹف•ûŒü‚ض–ٌ‚Pkm‚جڈٹ‚ة‚ ‚é‹Œگü‹وٹش
‚جژR‰؛‰wگص‚ض‚â‚ء‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پB
…‚»‚à‚»‚àژ„‚حڈي”ضگü‚ج“–ٹY‹وٹش‚ةڈو‚é‚ج‚ھڈ‰‚ك‚ؤ‚ب‚ج‚إپA‚ا‚؟‚ç
‚ج‰w‚à’m‚ç‚ب‚¢ƒڈƒP‚إ‚·‚ھپA10”N‹ك‚Œo‚ء‚ؤ‚é‚ج‚ة‚ـ‚¾چؤٹJ”‚ب‚ا‚ح
چs‚ب‚ي‚ê‚ؤƒiƒC—lژq‚إ‚·پB
Œ³‚ح‚Q–ت‚Qگü‚ج‰w‚¾‚ء‚½ژ–‚ھژf‚¦‚ـ‚·‚ثپB“¯‰w‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپA’أ”g‚ة‚و‚é
”يٹQ‚حڈ¬‚³‚©‚ء‚½‚à‚ج‚جپAگüکH‚»‚ج‚à‚ج‚ًˆعگف‚·‚é‚ج‚إگkچذŒم‚ة‰wژة
‚âŒ×گü‹´‚ح“P‹ژ‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
 
…چr‚ê‰ت‚ؤ‚½ƒzپ[ƒ€‚جƒRƒ“ƒNƒٹپ[ƒg‚جŒ„ٹش‚©‚çƒ^ƒ“ƒ|ƒ|‚ھچç‚¢‚ؤ‚é
‚ج‚ھ•¨”ك‚µ‚¢”½–تپAگ¶–½—ح‚ج‹‚³‚ف‚½‚¢‚ب•¨‚àٹ´‚¶ژو‚ê‚ـ‚·پB
‰w‘O‚جڈ¤“X‚â—X•ض‹ا‚حŒ’چف‚إ‚·‚ھپA‰w‚ھ–³‚‚ب‚ء‚ؤ‚àپu‰w‘Oپv‚ئŒ¾‚¤
•\‹L‚ج‚ـ‚ـ‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
‚±‚ج‹ŒژR‰؛‰w‚ج—ׂة‚حپA’nŒ³‚جژ©ژ،‘جپiژRŒ³’¬پj‚ھŒڑگف‚µ‚½ˆش—ى”è‚ھ
‚ ‚è‚ـ‚·پB‘±‚¯‚ؤƒ\ƒŒ‚ًŒ©‚ة‚¢‚ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
‚³‚ؤڈي”ضگü‚ج‹Œگü‹وٹش‚إ‚·‚ھپA‹{ڈ錧ژRŒ³’¬‚جژR‰؛‰wگص’n‚ة—ˆ‚ؤ
‚¨‚è‚ـ‚·پB…Œ»چف‚ح–w‚ا‚ھچX’n‚ئ‰»‚µ‚½‰wگص‚ة‰،‚ةپu‘ه’n‚ج“ƒپv‚ئ
–¼•t‚¯‚ç‚ꂽˆش—ى”è‚ھŒڑ‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚½پB
 
“¯’¬‚ح‘¾•½—mپiگه‘نکp‚ئŒ¾‚¤‚ج‚©پHپj‚ة–ت‚µ‚½’¬‚إ‚ ‚èپA‚±‚جژR‰؛‰w
گص’n‚إٹCٹفگü‚©‚ç–ٌ1.2km‚ج’n“_‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ھپA“Œ“ْ–{‘هگkچذ‚إ‚ح
637–¼‚ج’¬–¯‚ج•ûپX‚ھ–S‚‚ب‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB
چLڈê‚ً‰~Œ`‚ةˆح‚قٹ´‚¶‚إ•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚éچ•‚¢Œن‰eگخ‚ج‘ه•”•ھ‚ھپAگkچذ‚إ
‹]گµ‚ة‚ب‚ء‚½گl‚½‚؟‚ج–¼•ë‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚ؤپA‰ü‚ك‚ؤچذٹQ‚ج‹°‚낵‚³‚ھ
•ھ‚©‚è‚ـ‚µ‚·‚ثپB
 
’أ”g‚إ”يٹQ‚ًژَ‚¯‚é‘OŒم‚ج’¬‚جژتگ^‚àچع‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB“S“¹‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ح
ژR‰؛‰w‚ئژں‚جچ⌳‰w‚ج‚Q‰سڈٹ‚ھ“¯’¬“à‚ة“–‚½‚è‚ـ‚·پB
…ژR‰؛‰w‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ح‰½‚ئ‚©Œ´Œ^‚ً—¯‚ك‚ؤ‚é‚و‚¤‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·‚ھپAŒ©‚½‚ç
ƒzپ[ƒ€‚جڈم‚ةڈو—pژش‚ھچع‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ثپB‚â‚ح‚èژ©‘R‚ج—ح‚حˆج‘ه‚إ‚·پB
چ⌳‰w‚حŒ×گü‹´‚ئƒ\ƒm—ׂة‚ ‚ء‚½ŒِڈOƒgƒCƒŒˆبٹO‚ج‘S‚ؤ‚ھ‰ں‚µ—¬‚³‚ê
‰wژة‚حگصŒ`‚à‚ب‚ڈء‚¦‚½‚و‚¤‚إ‚·پB
‚»‚µ‚ؤ‹ŒژR‰؛‰w•t‹ك‚©‚ç“ى‚ج‹Œگü‹وٹش‚حپAƒoƒCƒpƒX“¹کH‚ض‚ج“]—p‚ھ
Œˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚µ‚ؤپA‚ـ‚¾‘ه•”•ھ‚ھچHژ–’†‚إ‚ح‚ ‚è‚ـ‚·‚ھچ،Œم‚ج“WٹJ
‚ھٹْ‘ز‚³‚ê‚ـ‚·پB…‘OŒü‚«‚ة•œ‹Œ‚µ‚ؤچs‚‚ج‚à‘هگط‚بژ–‚إ‚·‚وپB
 
‘±‚¢‚ؤ‚ھ‚P‚آ“ى‚ة‚ ‚éچ⌳‰w‚إ‚·‚ھپA‚±‚؟‚ç‚àگV‚µ‚‘¢‚è’¼‚³‚ꂽ
Œ»چف‚ج‰w‚©‚猩‚ؤچs‚«‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
…ƒfƒUƒCƒ“‚حگو’ِŒ©‚ؤ‚«‚½ژR‰؛‰w‚ةژ—‚ؤ‚¨‚èپAƒRƒR‚àچ‚‰ث‰w‚إ‚·‚ھپA
Œًٹ·گف”ُ‚ج‚ب‚¢–_گüƒzپ[ƒ€‚ج‰w‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ثپB
‚±‚؟‚ç‚à‰w‘O‚ة‚حƒچپ[ƒ^ƒٹپ[‚ھگ®”ُ‚³‚êپA‹ك‚‚ة‚ح“¹‚ج‰w‚àڈo—ˆ‚ؤ
‚¨‚èپAگV‚µ‚¢‰w‘O‚ج’¬‚ئ‚µ‚ؤگ®”ُ‚³‚ê‚ؤ‚éٹ´‚¶‚إ‚µ‚½پB
…•œ‹ŒŒم‚ةٹJ’ت‚µ‚½گVگü‹وٹش‚إ‚حچ‘“¹‚Uچ†گü‚ةچإ‚à‹ك‚¢‰w‚ب‚ج‚إپA
ƒoƒX‚إ’ت‚éٹدŒُ‹q‚àژو‚èچ‚à‚¤‚ئ‚µ‚½”‘z‚ب‚ج‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
 
چ‚‰ث‰w‚ب‚ج‚إگüکH‚ج‰؛‚ج‚PٹK‚ھڈoژD‘‹Œû‚â‰üژDŒû‚ة‚ب‚èپAƒRƒR‚à
ٹبˆصˆد‘ُ‰w‚إ‚µ‚½پB…ژ©“®‰üژD‹@‚ح‚ب‚Suica‚جƒJپ[ƒhƒٹپ[ƒ_پ[‚إ‚·پB
‚»‚µ‚ؤ‰w‘O‚ة•ھ‚©‚è‚â‚·‚¢’nگ}‚ھ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
ٹCٹف‚ة‹ك‚¢ڈٹ‚ةپuŒ§“¹‘ٹ”nکj—گüپv‚ئ‚µ‚ؤٹDگF‚ج‚ظ‚عˆê’¼گü‚ج“¹کH
‚ھ•`‚©‚ê‚ؤ‚ـ‚·پB‚»‚ج‰؛‚ةپuچHژ–’†پv‚ئ‚ ‚é‚و‚¤‚ةپAŒ§“¹‚ئ‚µ‚ؤ‚ح‚ـ‚¾
ˆê•”‚ج‹وٹش‚µ‚©ٹJ’ت‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپBƒRƒŒ‚ھŒ³‚جڈي”ضگü‚إ‚·‚ثپB
گkچذ‘O‚جچ⌳‰w‚ةٹض‚µ‚ؤ‚ح‹Lچع‚ح‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ھپAŒ»چف’n‚©‚çٹCٹف‚ج
•ûŒü‚ضŒü‚©‚ء‚ؤپA‹Œڈي”ضگü‚ئŒً‚ي‚é•س‚肾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB…‚â‚ح‚è
‚Pkm‚®‚ç‚¢‚©‚بپH’nگ}ƒAƒvƒٹ‚ًژQچl‚ةژش‚إˆع“®‚µ‚ؤ‚ف‚ـ‚µ‚½پB
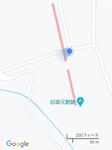 
…GPS‚إ‚حٹm‚©‚ةƒRƒR‚ج”¤‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ھپA‚±‚ج•t‹ك‚ج‹Œگü‹وٹش‚حگV‚µ‚¢
ƒoƒCƒpƒX“¹کH‚ض‚ج“]—p‚ھŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¨‚èپAٹù‚ةچHژ–‚ھژn‚ـ‚ء‚ؤ‚ـ‚·‚ج‚إ
ƒ\ƒŒ‚炵‚¢•µˆح‹C‚ح‘S‚‚ ‚è‚ـ‚¹‚ٌ‚ثپB
 
ƒAƒvƒٹ‚ج’nگ}ڈم‚ةپu∴پv…‹Œگص‚ج’nگ}‹Lچ†‚ھ‚ ‚é‚ج‚حپAگ³ٹm‚ة‚حچ¶‚ج
‰و‘œ‚إƒuƒ‹ƒhپ[ƒUپ[‚ھ‹ڈ‚é•t‹ك‚¾‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·‚ھپA‚»‚à‚»‚à“y’n‚ج
چ‚’لچ·‚©‚猾‚ء‚ؤ‚à•sژ©‘R‚إ‚·پB
…Œم‚إ’²‚ׂؤ‚ف‚é‚ئپA‚±‚جƒoƒCƒpƒX“¹کH‚حچؤ‚ر’أ”g‚ھ—ˆ‚ؤ‚à–h”g’ç‚ج
–ً–ع‚ھ‰ت‚½‚¹‚é‚و‚¤‚ة‚ئ‚جژ–‚إپAŒ³‚جگüکHگص‚و‚èƒJƒiƒٹچ‚‚گ“ڈم‚°‚µ‚ؤ
‘¢‚ç‚ê‚ؤ‚é‚ج‚¾‚»‚¤‚ؤ‚·پB
ٹ®گ¬‚ح‚ـ‚¾ڈ‚µگو‚ة‚ب‚è‚»‚¤‚إ‚·‚ھپA’Zٹْٹش‚إپi‚ئ‚حŒ¾‚ء‚ؤ‚à10”N‚ح
Œo‚ء‚ؤ‚é‚©پjƒRƒR‚ـ‚إ•µˆح‹C‚ھ•د‚ي‚é—ل‚à’؟‚µ‚¢‚©‚بپH
‚»‚µ‚ؤپA‚±‚ج’n“_‚©‚ç‹Œگü‰ˆ‚¢‚ةڈ‚µ“ى‰؛‚µ‚½ڈٹ‚ةپA’أ”g‚ج”يٹQ‚ً
ژَ‚¯‚½ڈ¬ٹwچZ‚جŒڑ•¨‚ھ•غ‘¶‚³‚ê‚ؤ‚é‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إŒ©‚ةچs‚ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚½پB
 
چZ–¼‚ًژRŒ³’¬—§’†•lڈ¬ٹwچZ‚ئŒ¾‚¤‚و‚¤‚إ‚·‚ھپAچ،ژ‚جٹ´‚¶‚ج‚¨ں—ژ‚ب
چZژة‚ھپA‰“–ع‚ة‚ح–³ژ–‚ب—lژq‚إژc‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
چZژة‚ج‘O‚ة‚ ‚éڈ¼‚ج–ط‚حپAŒ³پX•~’n“à‚ة‚ ‚ء‚½–ٌ20–{‚جƒNƒچƒ}ƒc‚ج
‚¤‚؟پA’أ”g‚ة‘د‚¦‚ؤژc‚ء‚½‚P–{‚ًپuٹïگص‚جˆê–{ڈ¼پv‚ئ‚µ‚ؤˆعگA‚µ‚½•¨‚¾
‚»‚¤‚إ‚·پB…ٹm‚©ژO—¤‚ج•û‚ة‚à“¯–¼‚جڈ¼‚ھ‚ ‚ء‚½‚و‚¤‚ةژv‚¢‚ـ‚·‚ھپB
 
گkچذ”گ¶ŒمپA’†•lڈ¬ٹwچZ‚ح2013”N‚ة—ׂجڈ¬ٹwچZ‚ئچ‡•¹‚³‚ê‚ـ‚µ‚½‚ھ
Œڑ•¨‚حˆê•”‚ًڈœ‚¢‚ؤژو‚è‰َ‚µ‚ً–ئ‚êپAچ،”N‚ج‚VŒژ‚©‚çگkچذ‚جˆâچ\‚ئ
‚µ‚ؤŒِٹJ‚³‚ê‚éژ–‚ة‚ب‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚·پB
…–K–âژ‚حƒ\ƒmچHژ–’†‚¾‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپAچZژة‚جٹOٹد‚ئٹO‚©‚猩‚¦‚é•”•ھ
‚¾‚¯‚ھŒ©ٹwڈo—ˆ‚éڈَ‘ش‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚ـ‚µ‚½پB
 
گـٹp‚ب‚ج‚إژش‚ًچ~‚è‚ؤژüˆح‚ًŒ©‚ؤ‚ف‚ـ‚·پB‰“–ع‚ة‚حƒLƒŒƒC‚ةŒ©‚¦‚½
چZژة‚إ‚·‚ھپA‚QٹK‚ج“Vˆن•t‹ك‚ـ‚إ’أ”g‚ھ”ي‚ء‚½‚و‚¤‚إپA“à•”‚حٹ®‘S‚ة
”j‰َ‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپAگ…ˆت‚ًژ¦‚·ƒvƒŒپ[ƒg‚ھƒJƒiƒٹچ‚‚¢ˆت’u‚ة‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پB
•ٌ“¹‚ب‚ا‚جژ‘—؟‚ة‚و‚é‚ئپA“¯ڈ¬ٹwچZ‚حگkچذ”گ¶ژ‚àژِ‹ئ’†‚إ‚µ‚½پB
’أ”g‚ھٹwچZ‚ـ‚إ“’B‚·‚é‚ـ‚إ‹ح‚©10•ھ‚جژٹش‚µ‚©–³‚پAژw’肳‚ꂽ
”ً“ïڈêڈٹ‚ـ‚إ’لٹw”N‚جژq‹ں‚ج‘«‚إ‚حٹش‚ةچ‡‚ي‚ب‚¢‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپAچZ’·
گوگ¶‚جژwژ¦‚إژ™“¶‚âگEˆُ‚ب‚ا–ٌ90–¼‚ھ‰®ڈم‚ة”ً“ïپB
‰®چھ— ‚ض‚ج‘qŒة‚إˆê”س‰ك‚²‚µ‚½ŒمپAژ©‰q‘à‚جƒwƒٹƒRƒvƒ^پ[‚ة‚و‚ء‚ؤ
‘Sˆُ‚ھ‹~ڈ•‚³‚ꂽ‚»‚¤‚إ‚·پB
…ƒzƒ“ƒg‚ةٹë‹@ˆê”¯‚ئŒ¾‚¤‚©پA‘Sˆُ‚ھڈ•‚©‚ء‚½‚ج‚ئگkچذŒم‚àژ{گف‚ھ
•غ‘¶‚³‚êپAƒLƒŒƒC‚ب‰ش‚إڈü‚ç‚ê‚ؤ‚é‚ج‚ھ‹~‚¢‚ج‚و‚¤‚ةٹ´‚¶‚ـ‚µ‚½پB
’P‚ب‚é”pگüگصڈ„‚肾‚¯‚إ‚ب‚پA‹ح‚©‚ب‚ھ‚ç•×‹‚ة‚ب‚ء‚ؤ—ا‚©‚ء‚½‚ئ
ژv‚¢‚ـ‚·پBŒِٹJ‚³‚ê‚éژ{گف‚ئ‚µ‚ؤ‚جƒIپ[ƒvƒ“‚ئپAƒoƒCƒpƒX“¹کH‚ھٹ®گ¬
‚µ‚½‚çپAچ،“x‚حژ©•ھ‚جژش‚إ‚ـ‚½—ˆ‚ؤ‚ف‚و‚¤‚©‚بپH
‚»‚ٌ‚بٹ´‚¶‚إ‹Œگü‹وٹش‚ج—·‚ح‘±‚«‚ـ‚·پB
ƒoƒCƒpƒX“¹کH‚ة“]—p‚³‚ê‚é—\’è’n‚ج‚¤‚؟پAگوچs“I‚ةٹJ’ت‚µ‚ؤ‚é‹وٹش‚ً
ژہچغ‚ة‘–‚ء‚ؤپAچ،‰ٌ‚ج–ع“I’n‚إ‚ ‚éگV’n‰w‚ض‚ئŒü‚©‚¤ژ–‚ة‚µ‚ـ‚µ‚ه‚¤پB
 
…Œ³پXƒ\ƒŒ‚ظ‚اŒً’ت—ت‚ح‘½‚ƒiƒC‚ج‚إ‚µ‚ه‚¤پB•ذ‘¤‚Pژشگü‚ج“¹کH‚إ‚·پB
–h”g’ç‚ج–ً–ع‚ًŒ“‚ث‚ؤŒ³‚جگüکH‚و‚èگ“ڈم‚°‚³‚ꂽ’z’ç‚جڈم‚ً‘–‚é‚ج‚إپA
ڈ]—ˆ‚ح“¥گط‚¾‚ء‚½‚و‚¤‚بکe“¹‚ح—§‘جŒًچ·‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
”pگüگص‚ھ“¹کH‚ة“]—p‚³‚ꂽ—ل‚ح‘½‚‚ ‚è‚ـ‚·‚ھپAژ‘م‚ئ‹¤‚ة’iپX‚ئ
ڈ¤“X‚âڈZ‘î‚ھ‘‚¦‚ؤ‚¢‚‚à‚ج‚إپAƒ\ƒŒ‚ھ‚ـ‚¾‚جڈَ‘ش‚جپu“]ٹ·‚µ‚ؤ‚·‚®پv
‚جڈٹ‚حژ„‚àڈ‰‚ك‚ؤ‘–‚ء‚½‚©‚à’m‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB
…‚»‚ج‚¤‚؟پuƒRƒR‚ھگüکH‚¾‚ء‚½پvژ–‚àˆê”ت‚ة‚ح’m‚ç‚ê‚ب‚‚ب‚é‚ٌ‚إ‚µ‚ه‚¤پB
 
’ِ‚ب‚‚µ‚ؤ•ں“‡Œ§‚ة“ü‚è‚ـ‚·پB…چsگ‹و‰و‚ھگV’n’¬‚ئŒ¾‚¤‚¾‚¯‚ ‚ء‚ؤپA
ˆعگف‹وٹش‚إ‚حگV’n‰w‚¾‚¯‚ھ•ں“‡Œ§‚ب‚ٌ‚إ‚·‚ثپB
“à—¤•ûŒü‚ًŒ©‚é‚ئپAڈ‚µ—£‚ꂽڈٹ‚ةگV‚µ‚¢ڈي”ضگü‚ھŒ©‚¦‚ـ‚µ‚½پB
‹——£‚ة‚µ‚ؤ500‚چ‚®‚ç‚¢‚©پH’iپX‚ئچ‡—¬“_‚ھ‹ك•t‚¢‚ؤ‚¨‚è‚ـ‚·پB
…’¼گعٹضŒWƒiƒC‚ج‚إ‚·‚ھگد”N‚ج‹^–â‚ً‚P‚آپAŒ§“¹‚ب‚ا‚ة‚ح“¹کH”شچ†‚ئ
•ت‚ةپuپ›پ›پ¢پ¢گüپv‚ف‚½‚¢‚ب–¼ڈج‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·‚و‚ثپBƒRƒR‚حپu‘ٹ”nکj—گüپv
‚ئŒ¾‚¤‚ج‚إ‚·‚ھپA“¹کH‚ھ•،گ”‚جŒ§‚ةŒ×‚éڈêچ‡پA–¼‘O‚ح‚ا‚£Œˆ‚ك‚é‚ج‚³پH
—¼Œ§‚ھکb‚µچ‡‚¤‚ج‚©پAŒ§‹«‚إ–¼ڈج‚à•د‚ي‚ء‚ؤ‚µ‚ـ‚¤‚ج‚©پH
…“ء‚ةگ³‰ً‚ح‹پ‚ك‚ؤ‚ـ‚¹‚ٌ‚ھگج‚©‚ç‚ج“ن‚ب‚ج‚إ‚·‚وپiژ©•ھ‚إ’²‚ׂëپjپB
 
‚»‚µ‚ؤگV’n‰w‚ة“’…‚إ‚·پBŒك‘O’†‚ة—ٌژش‚إ–kڈم‚µ‚ؤ‚«‚½ژ‚ة‚àڈ‘‚«
‚ـ‚µ‚½‚ھپAƒRƒR‚à’أ”g‚ج”يٹQ‚ًژَ‚¯‚ؤ‰wژة‚ئ’âژش’†‚ج—ٌژش‚ھ‰ں‚µ
—¬‚³‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚¢پAŒ³‚ج’n“_‚و‚è300‚چ‚ظ‚ا“à—¤‘¤‚ةگV’z‚³‚ê‚ـ‚µ‚½پB
‚·‚®‚ةڈ]—ˆ‚ج‹وٹش‚ئ‚جچ‡—¬“_‚ةژٹ‚é‚ج‚إ’nڈم‰w‚إ‚·پB
‰w‘O‚ة‚حگV‚µ‚¢ƒrƒWƒlƒXƒzƒeƒ‹پi‚ا‚ٌ‚بژù—v‚ھ‚ ‚é‚ج‚©پHپj‚ب‚ٌ‚©‚à
Œڑ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚µ‚½پB
ƒRƒR‚àٹبˆصˆد‘ُ‰w‚ج‚و‚¤‚إ‚·‚ھپA‘‹Œû‚ھ’ڑ“x•آ‚ـ‚è‚©‚¯‚ؤ‚éƒ^ƒCƒ~ƒ“ƒO
‚¾‚ء‚½‚ج‚إپAŒW‚ج‚¨‚¶‚³‚ٌ‚ھپu‰½‚©—pپHپv‚ف‚½‚¢‚ب‘ش“x‚إ‚µ‚½‚ثپB
‚±‚ٌ‚بڈٹ‚إ•،ژG‚بگط•„‚ئ‚©”ƒ‚ي‚ب‚¢‚©‚çپA‹A‚èژx“x‚ةگê”O‚µ‚ؤƒCƒC‚¼پB

‰w‚ً‰ك‚¬‚½ڈٹ‚ة‚ ‚铹کH‹´‚©‚ç
ڈي”ضگü‚جگüکH‚ًŒ©‚ؤ‚ف‚ـ‚·‚ئپA
‘ه‚«‚ƒJپ[ƒu‚µ‚ؤ‚é’n“_‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB
‰کH‚ج‰و‘œ‚إŒ¾‚¤‚ئ‚±‚ج’n“_‚إ‚µ‚ه‚¤پB
Œ³‚جگüکH‚ح‰œژè‚ج•û‚©‚ç—ˆ‚ؤƒRƒR
‚إƒJپ[ƒu‚¹‚¸پAŒü‚©‚ء‚ؤچ¶‘¤‚ج“¹کH
‚ج•û‚ض’¼گi‚·‚é‚و‚¤‚بگüŒ`‚¾‚ء‚½
‚ئژv‚ي‚ê‚ـ‚·پB
…ƒRƒR‚ـ‚إ‚ھگkچذˆبŒم‚ةگVگü‚ئ‚µ‚ؤ•œ‹Œ‚µ‚½‹وٹش‚ة‚ب‚è‚ـ‚·‚©‚çپA
ˆê‰Œ©‚½‚¢ڈٹ‚ح‘S•”Œ©‚½‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إگه‘ن‹َچ`‚ض‹A‚è‚ـ‚µ‚ه‚¤پB

‹A‚è‚حچ‘“¹‚Uچ†گüپ`چ‘“¹‚Sچ†گü‚إ
گ^‚ء’¼‚®‹A‚ء‚½‚ٌ‚إ‚·‚ھپAژٹ‚éڈٹ‚ة
’أ”g‚إگZگ…‚µ‚½’n“_‚ًژ¦‚·•Wژ¯‚ھ
‚ ‚é‚ٌ‚إ‚·‚وپB
‚±‚ج•س‚è‚جچ‘“¹‚Uچ†گü‚ء‚ؤپA‘ه‘ج‚ج
‹وٹش‚إٹCٹف‚©‚ç‚Qkm‚ح—£‚ê‚ؤ‚é‚ئ
ژv‚¤‚ٌ‚إ‚·‚ھژ©‘R‚ج—ح‚ء‚ؤƒzƒ“ƒg‚ة
ƒXƒS‚¢‚ٌ‚إ‚·‚ثپB…“ق—ا‚ةڈZ‚ٌ‚إ‚é‚ئ
•ھ‚©‚ç‚ب‚¢ژ–ژہ‚إ‚·پB
‚ئŒ¾‚¤ژ–‚إپA’·‚ç‚‚ج”Oٹè‚إ‚ ‚ء‚½ڈي”ضگü‚جڈو‚è’ׂµ‚ئپAگkچذˆبŒم‚ة
گüکH‚ھˆعگف‚³‚ꂽ‹وٹش‚جŒ©ٹw‚à–³ژ–‚ةڈI‚¦‚éژ–‚ھڈo—ˆ‚ـ‚µ‚½پB
|
|